モーツァルトの音楽についてと、モーツァルトへのよくある誤解?
いつもお世話になっているぴあのピアノ♪というサイトに興味深い記事が。大変興味深いのだが少し気になる点が…
ぴあのピアノ♪の当該記事に分かりやすい要約があるが、元記事もあるのでリンク
吉松隆は個人的に大変好きな作曲家である。が、モーツァルトへの認知はやや疑問。そもそも吉松隆はモーツァルトを評価していない。
西村朗と吉松隆の クラシック大作曲家診断という本でもモーツァルトへの評価は散々と言える。Amazonのレビューを見れば何となく察せられる。
もちろんモーツァルトを不当に貶しているわけではなく、世間のモーツァルトへの印象―それはモーツァルトを使ってお儲けしたい人たちによって作られた―について話していたりする。そもそも吉松隆は「売れっ子」作曲家への評価は高い。これは他の文章でもたびたび見受けられる。なので別にモーツァルトを見下しているわけではないのだが…
モーツァルトはわかり易い音楽なのか
吉松隆氏によると、
なにしろ「音の純粋な心地よい響き」だけで出来ていて、聴き手に「思想を押しつけること」も「理解を強いること」もしないのだから、嫌われる理由もない。
しかし、それは逆に言うと、「なにも引っ掛かるところのない(空気や水のような)音楽」ということでもあり、万人に好かれるけれど魂を揺さぶるわけではない、要するに「思想や内容が全くない音楽」というとらえ方も出来ることになる。(引用:モーツァルトのピアノ協奏曲な世界)
モーツァルトは聴衆に「理解を強いること」もしないのだろうか。これは本当なのだろうか。
ニコラウス・アーノンクールの『古楽とは何か―言語としての音楽』によるとバッハ以降の後期バロック時代に、複雑で一部の通だけが理解できる音楽から誰でも理解できるへと変化した。
そして
当然のこととして、モーツァルト自身は、バッハ以後の新たな〈感情の音楽〉をきっぱりと拒絶し、分かりもしないのに美しいと感じる聴き手を〈パパゲーノ〉と呼んだ。彼はこうしたことを非常に嘆かわしいと考え、自分はただ通人のためにのみ曲を書いているのだと強調している。(中略)聴衆が音楽の知識と一般教養を備えていることを前提としている。
(中略)父親は、モーツァルトがあまりにも通人だけを相手にしているといって気遣った。「おまえは単に音楽的な聴衆だけでなく、非音楽的な聴衆のことも考えて仕事をした方がよいと思う。・・・・・いわゆる民衆を忘れてはいけない。(中略」(1780年12月))。
(中略)モーツァルトの同時代人だちは彼の作品を極端なコントラストに満ち、色彩が強く、扇情的で、衝撃的だと述べている。(引用:ニコラウス・アーノンクール『古楽とは何か―言語としての音楽』p219~220)
レオポルド・モーツァルトがアマデウス・モーツァルトにもっと誰でも分かる音楽も書いた方が良いと手紙で助言したのは確かだ。
そして聴衆が備えている前提の『音楽の知識と一般教養』は現代に生きる我々にはなかなか難しい。クラシック音楽の専門家でも把握していないものも含む。
ついでに、
聴衆はあらゆる新しいアイディア、楽器法の効果、和声的・旋律的な特徴に気づき、積極的に賛否を表明した。(中略)モーツァルトは、楽章の間、それどころか演奏中に拍手が起きてもまったく驚いたりしない。それをあらかじめ予想してさえいるのだ。(中略)おそらく音楽の一部が興奮した聴衆の歓声で聞こえなくなることもあったから、繰り返しはそれを補足する意味を担っていた。むろん内省的なアンダンテの後では騒がしい喝采は控えられた。(引用:ニコラウス・アーノンクール『古楽とは何か―言語としての音楽』p319~320)
とあり、当時の聴衆の音楽的素養の高さが非常に高いことが分かる。
何から何まで引用してしまったら転載になってしまうので気になる人は本を読んでみてください。
まあ、モーツァルトの音楽がどれほど音楽的教養が求められていようとも、現代を生きる我々はそれを知る術はほとんどないのだが…(例えクラシック音楽の専門家であっても)
モーツァルトの美しい響き
モーツァルトの音符たち―池辺晋一郎の「新モーツァルト考」によると、(大雑把要約)
ドミソの和音、すなわちその調の音階のⅠ度、Ⅲ度、Ⅴ度の和音は長三和音。それは自然倍音なので自然界に存在している音と言える。
それが心地良い響きに繋がっているらしい。これはモーツァルトに限らず先人たちが積み上げてきた作曲法によるものだけど、モーツァルトがトニックの扱いに群を抜いて長けているイメージがある。
というわけで、『「音の純粋な心地よい響き」だけで出来ていて』というのが現在のモーツァルト人気の大きなところだろう。
モーツァルトの短調
そこで、29歳の時のニ短調のピアノ協奏曲第20番あたりから、モーツァルトは意識的に「短調」の世界に踏み込む。
しかし、これは当時の彼の音楽のファンにとっては「不協和音で曲を書き始めた」みたいなものだったらしく、あっと言う間に人気急落。定収入を得られるはずの予約演奏会にも客が集まらなくなり、晩年の「不遇」「貧乏」そして35歳という若さでの夭逝に繋がってゆく。(引用:モーツァルトのピアノ協奏曲な世界)
現代を代表する作曲家である吉松隆の文章なので大変恐縮なのだが、とは言え違うのではないかというのが正直な感想。
モーツァルトはソナタ形式の音楽をたくさん書いた。まあ、ソナタ形式でなくてもいいのだが。曲の中でずっと長調なんてことはもちろんほとんどない。途中でかなりシリアスでショッキングな短調に入ることは多々ある。というか作曲家人生前半の神童時代はかなりシリアスな短調も書いている。もちろん神童時代から大人気だったので、その短調も受け入れられていたのだろう。
確かにウィーンはイタリア流の音楽を受け継いでいて、シリアスなフランス流とは違う。しかしイタリア流とは言えヴィヴァルディの『四季・冬』のような曲が作られる土壌はある。(当時のウィーンでは知る由もないだろうが。)ちょっと短調を主とした曲というだけでモーツァルトから離れるというのは当時のウィーン人を舐めすぎているのではないかと思う。
ちなみに予約演奏会に客が入らなくなったのは、
なお、ウィーンで演奏会が開きにくくなった原因については、伝統的に「ウィーン人の趣味がモーツァルトから離れていったため」といった説明がされることが多かったが、当時のウィーンはトルコとの戦争などによってインフレが高まっており、演奏活動を支えていた貴族たちの中にもウィーンを離れる者が多かったことなどから、モーツァルトの人気だけが落ちたのではなくウィーンでの演奏会文化全体が低調化していたと考える方が妥当なようである。
(引用:モーツァルト時代の演奏会、『200CDモーツァルト』(立風書房、1997)
との通り、モーツァルトの音楽性によるものとは考えにくいです。
シンプル
シンプルであることは、いわゆる「単純」ということではありません。オペラを聴けばよくわかるように、モーツァルトは人生の複雑な面、人間の両面性というか、シンプルでないものをシンプルに見せる能力がすごい。(引用:ピアノの名曲 イリーナ・メジューエワ著)
モーツァルトの音楽は一見(一聴?)すれば単純で分かりやすいように思える。しかし短いパッセージ、少ない音符で途轍もない情報量、起承転結が完璧に示されている。だから偉いというわけではないが、モーツァルトの音符は1つあたり最も価値があるだろう。

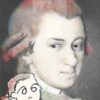





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません